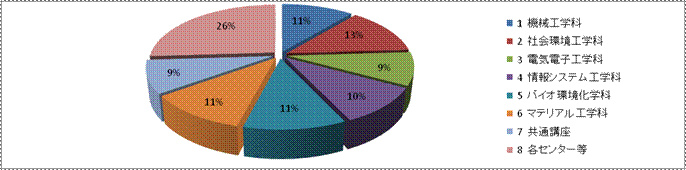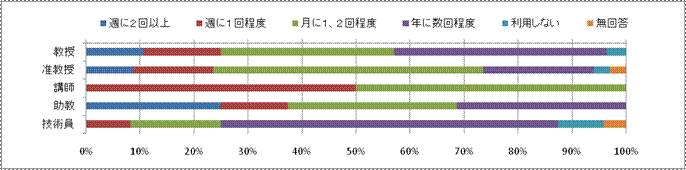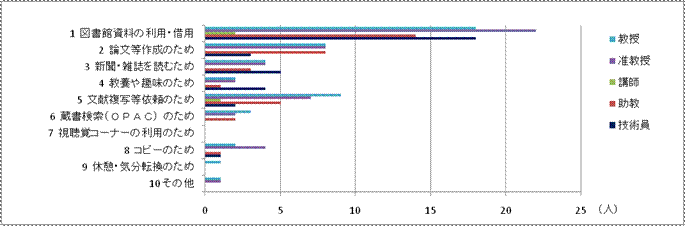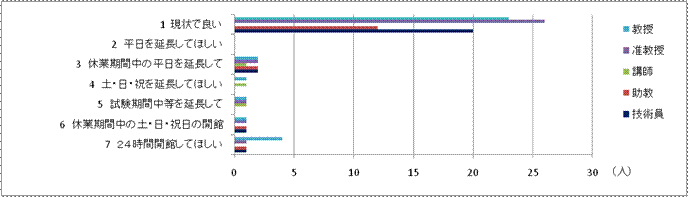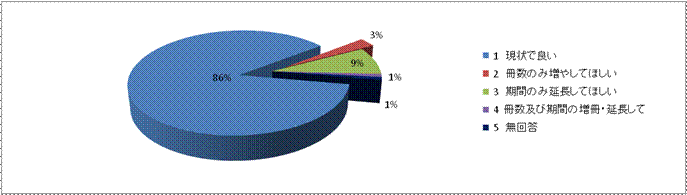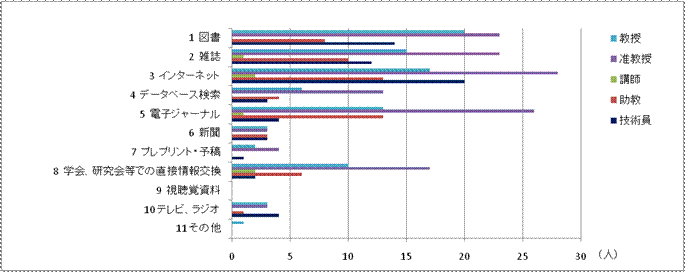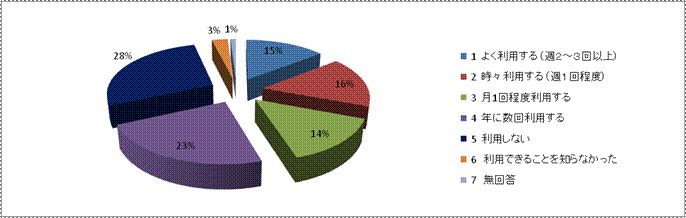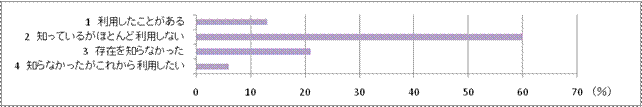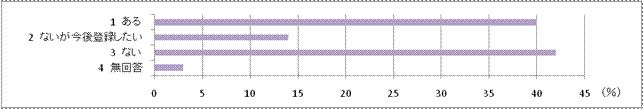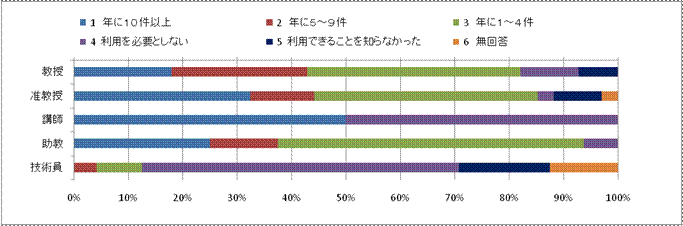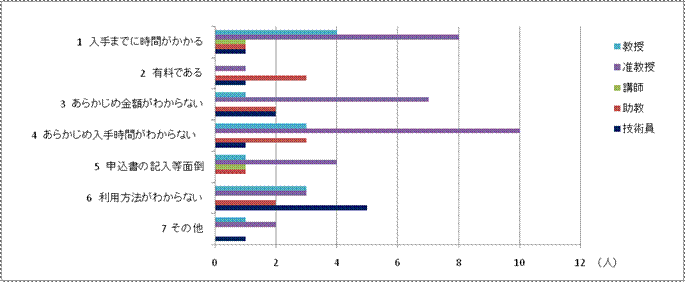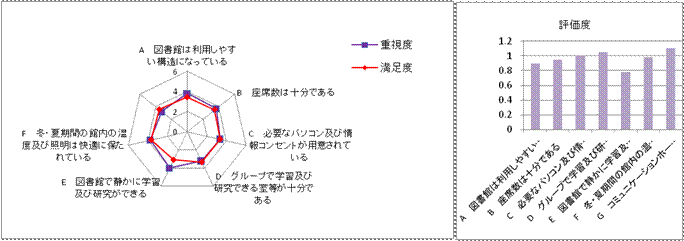|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�}���ٗ��p�Ɋւ���A���P�[�g���� |
|
|
|
|
|
|
|
�i�����E�Z�p���ҁj |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �� �P |
���Ȃ��̐E�������q�˂��܂��B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�@��@�@�@�@�@�@�@�@�@�� |
���� |
�y���� |
�u�t |
���� |
�Z�p�� |
�v |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
34 |
2 |
16 |
24 |
104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�� |
0.27 |
0.33 |
0.02 |
0.15 |
0.23 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �@��������S�̂łT�U���Ɏ~�܂�A�Z�p�����V�T���ƍł������A�u�t���Q�T���ƒႩ�������̂́A�҂̍\���l����͑�w�S�̂̍\���l����Ƃقړ����x�Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł��܂��B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �� �Q |
���Ȃ��̏��������q�˂��܂��B |
|
|
|
|
|
|
|
|
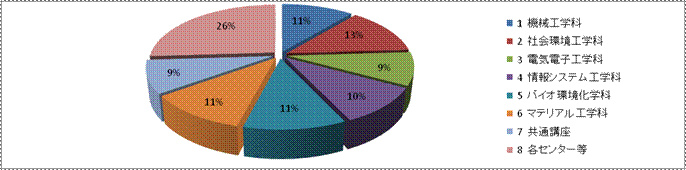
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �@�w�ȓ��̍\���l����Ɖ҂̏����l����ɑ傫�ȈႢ�͂���܂���B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �� �R |
�}���ق��ǂ̒��x���p���Ă��܂����B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
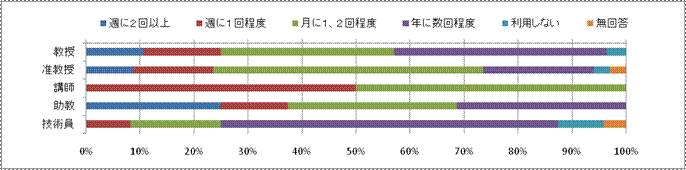
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �@
�T�ɂP����x�ȏ㗘�p����l�̊������Q�R���ƁA�O��̒����i�R�X�D�W��)��茸�����A�u�N�ɐ�����x�v�������p���Ȃ��l���S���߂����߁A�u���ɂP�A�Q����x�v�̗��p�҂��܂߂�ƂW���߂��ɒB���A�O����藘�p�p�x�͌����X���ɂ���܂��B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �� �S |
��ȗ��p�̖ړI�͂Ȃ�ł����B�i�O�ȓ��I���j |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
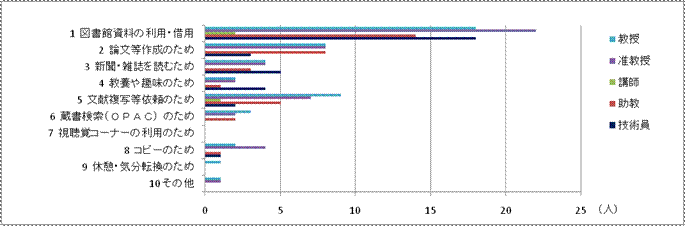
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �@�u�}���َ����̗��p�E�ؗp�v���҂̖�V�O�����߁A�����Łu�_�����쐬�̂��߁v(�Q�U��)�A�u�������ʓ��˗��̂��߁v(�Q�R��)�A�u�V���E�G����ǂނ��߁v(�P�T��)�������Ă��܂����A�u���{���̂��߁v�A�u�R�s�[�̂��߁v�͂P�O������Ă��܂��B |
| |
| �� �T |
�J�َ��Ԃɂ��Ă��q�˂��܂��B�i�����j |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
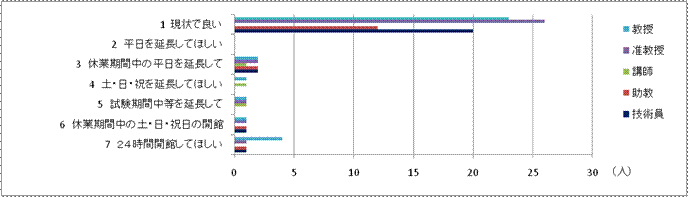
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �@�J�َ��Ԃ͑O������J�َ��Ԃ̌��������}��ꂽ���߁A�u����ŗǂ��v���O����葝���ĂW���߂����߂Ă��܂����A�u�x�Ɗ��Ԓ��̕������������āv�A�u�Q�S���ԊJ�ق��Ăق����v��]�ސ����P�����x�o����Ă��܂��B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �� �U |
�}���̑ݏo�����y�ъ��Ԃɂ��Ă��q�˂��܂��B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
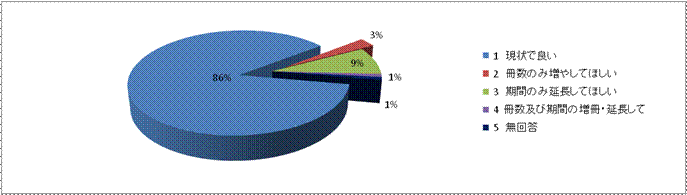
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �@�u����ŗǂ��v�Ƃ���l���X���߂��ɒB���A����ɖ������Ă��邱�Ƃ��킩��܂����A�u���Ԃ̂݉������Ăق����v����]����ӌ����P�����x����܂����B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �� �V |
�K�v�Ƃ�����╶���̓����i�y�є}�̂Ƃ��Ēʏ험�p����̂͂ǂ�ł����B�i�܂ȓ��I���j |
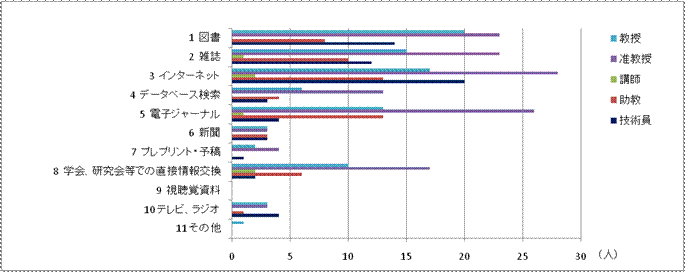 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �@
�K�v�Ƃ�����̓����i�͑O���ŌQ���đ��������u�}���v�A�u�G���v�ɑ���u�C���^�[�l�b�g�v����ԂɂȂ�A�u�d�q�W���[�i���v�̊������Q�O���߂��������āu�G���v�ɔ����Ă��܂��B���̂��Ƃ���R�̗��p�p�x�̌����X���̈���ƍl�����܂��B�u�w��A������ł̒��ڏ������v�ɑ傫�ȕω��͂Ȃ��A�u�f�[�^�x�[�X�����v�A�u�V���v�A�u�e���r�A���W�I�v�������Ă��܂��B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �� �W |
�u�`�Ɛ}���قƂ̊֘A�ɂ��Ă��q�˂��܂��B�i�����j |
|
|
|
|
|
|
|
|
��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� |
���� |
�y���� |
�u�t |
���� |
�Z�p�� |
�v |
�� |
|
|
|
|
|
|
|
|
1
�u�`�̒��Ŏw��}���E���E�}���Ƃ̊֘A��������Ă��� |
3 |
10 |
2 |
3 |
0 |
18 |
0.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2�@�a�E�m�G�����܂߂Đ}���ق̕����i��L�P�ȊO�j�ɂ��ču�`�̒��Ő������Ă��� |
3 |
7 |
1 |
0 |
0 |
11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 �����̎g�����╶�������̕��@�ɂ��ču�`�̒��Ő������Ă��� |
2 |
4 |
0 |
1 |
0 |
7 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 �}���قƂ̊֘A�͍u�`�̒��œ��ɐ������Ă��Ȃ� |
20 |
19 |
0 |
9 |
10 |
58 |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
�v |
28 |
40 |
3 |
13 |
10 |
94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �@�u�}���قƂ̊֘A�͍u�`�̒��œ��ɐ������Ă��Ȃ��v�Ƃ̉��������߂Ă������A�u�u�`�̒��Ŏw��}���E���E�}���Ƃ̊֘A��������Ă���v�Ƃ̉͂Q����Ɏ~�܂��Ă���A�O������ω����Ă��܂���B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �� �X |
���ݖ{�w�ł͖�4,000�^�C�g���̓d�q�W���[�i�������p�ł��܂����A�ǂ̒��x���p���Ă��܂����B |
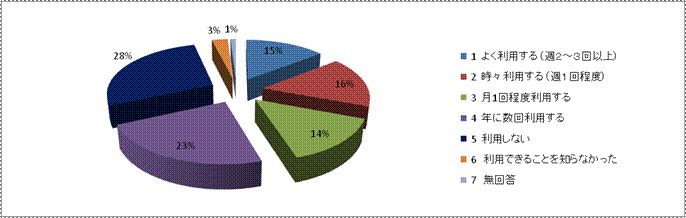
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �@�T�P��ȏ㗘�p����l�͑O����葝���ĂR�O���ɒB�������A�u���p���Ȃ��v�l�������ĂQ�W��������A���������ł��P�X���ɂȂ�܂��B���p���Ȃ����R�Ƃ��Ė{�w�ŗ��p�ł���d�q�W���[�i���Ɏ����̌����Ɋ֘A����G�����܂܂�Ă��Ȃ��P�[�X���l�����A�d�q�W���[�i�������̓������Ă��܂��B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �� 10 |
�k���H�Ƒ�w�@�փ��|�W�g���EKIT-R(�����Ƃ��[��)�ɂ��Ă��q�˂��܂��B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�@�@KIT-R(�����Ƃ��[��)�𗘗p�������Ƃ�����܂����B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
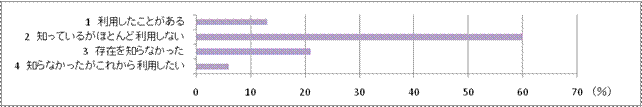
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�A�@�����́u�_���v����KIT-R�ɓo�^�������Ƃ�����܂����B |
|
|
|
|
|
|
|
|
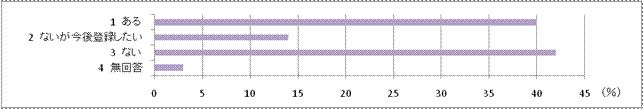
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �@KIT-R�i�����Ƃ��[��j�̔F�m�x�͂V�����Ă������ŁA�u���݂�m��Ȃ������v�l���Q�����x������̂̋����Ɍ����1�����x�ł��B�܂��AKIT-R�Ɂu�_���v����o�^���Ă���l�͋����̔������߁A�u����o�^�������v���܂߂�Ƌ����̂V���߂��ɒB���܂��B�����KIT-R�ւ́u�_���v���o�^�̑����A�[�������҂���܂��B |
| |
| �� 11�@�@ |
�{�w�ŏ������Ă��Ȃ�������}������w�������A�������ʁ^���ݑݎT�[�r�X���ǂ̒��x���p���Ă��܂����B |
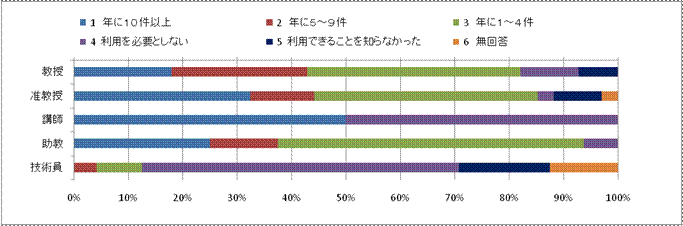
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �@�N�P���ȏ�̗��p�҂͂V���߂��ɒB���Ă��܂����A�O���Ɣ�r����ƂQ�����x�������Ă��܂��B����A�d�q�W���[�i���̕��y�ƃC���^�[�l�b�g�����ɂ���āA�u���p��K�v�Ƃ��Ȃ��v�Ƃ̉��O����P�O���������Ă��܂��B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �� 12 |
�������ʁ^���ݑݎT�[�r�X�𗘗p����ɂ�����iWEB�ォ����\���݂��ł��܂��j�A���_�͂���܂����B
�i�O�ȓ��I���j |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
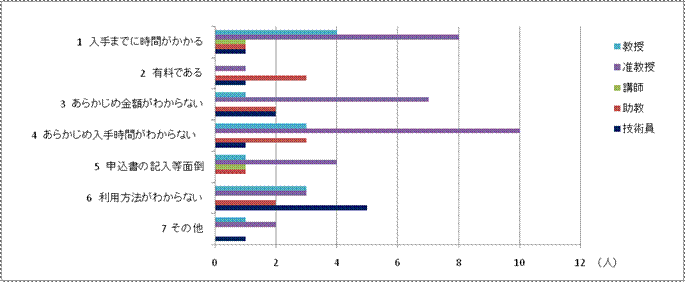
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �@���_�Ƃ��āu���炩���ߓ��莞�Ԃ��킩��Ȃ��v�A�u����܂łɎ��Ԃ�������v�A�u���炩���ߋ��z���킩��Ȃ��v�Ƃ������������߂�ӌ����������AWEB�ォ��̐\�����݂��܂߂��u���p���@���킩��Ȃ��v�Ƃ����T�[�r�X���̂̈ē��s�����w�E����Ă��܂��B�Ȃ��A���p�҂���̓T�[�r�X�ɖ������Ă��鐺���������Ă��܂��B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| �� 13 |
�ȉ��̍��ڂɂ��āA���Ȃ��̐}���قɑ���d���x�y�і����x�������������������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�킩��Ȃ����ڂ͉��Ȃ��Ă���낵���ł��B�j |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�@�@�{�y�ѐݔ��ɂ��� |
|
|
|
|
|
|
|
�]���x�@�i�����x�^�d���x�j |
|
|
|
|
|
|
|
|
��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� |
�d���x |
�����x |
�]���x |
|
|
|
|
A�@�}���ق͗��p���₷���\���ɂȂ��Ă��� |
3.80 |
3.43 |
0.90 |
|
|
|
|
B�@���Ȑ��͏\���ł��� |
3.69 |
3.49 |
0.95 |
|
|
|
|
C�@�K�v�ȃp�\�R���y�я��R���Z���g���p�ӂ���Ă��� |
3.33 |
3.36 |
1.01 |
|
|
|
|
D�@�O���[�v�Ŋw�K�y�ь����ł��鎺�����\���ł��� |
3.21 |
3.37 |
1.05 |
|
|
|
|
E�@�}���قŐÂ��Ɋw�K�y�ь������ł��� |
4.01 |
3.12 |
0.78 |
|
|
|
|
F�@�~�E�Ċ��Ԃ̊ٓ��̉��x�y�яƖ��͉��K�ɕۂ���Ă��� |
3.74 |
3.67 |
0.98 |
|
|
|
|
G�@�R�~���j�P�[�V�����z�[���̋�ԋy�ѐݔ��͏\���ɋ@�\���Ă��� |
3.20 |
3.55 |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
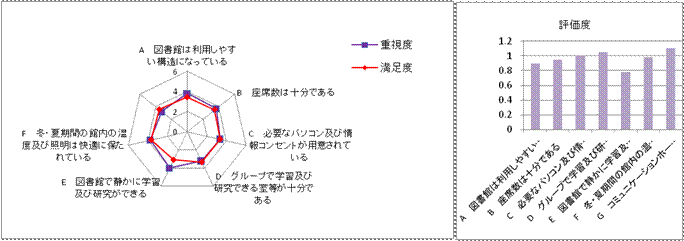
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �@�}���ق̎{�y�ѐݔ��Ɋւ��āA�d���x���x�ŏ������]���x�́u�d�@�}���قŐÂ��Ɋw�K�y�ь������ł���v�������ƂP�t�߂ɂ���A�����ނ˖����ł���ɂ���܂��B�}���ق̑��E���z�������]���Ɍ��т��Ă��܂��B�Ȃ��A�ۑ�Ƃ��ꂽ�u�Â��Ɋw�K�y�ь����ł���v���Â��肪�}���ł���A���㉽�炩�̑��߂��܂��B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
���̑��̈ӌ� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
��@�@�@�@�@�@�@�� |
�� |
�� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�ٓ��ւ̓����W |
2 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
���p���W |
4 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
���̑� |
2 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
���@�@�@�@�@�@�@�@�v |
8 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �@�}���ُo�����̑��݂����߂�ӌ��̑��A�ٓ��ł̈��H��b�����ȂNJw���̃}�i�[��������߂�ӌ������Ă��܂��B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|